



![]()
1957年3月6日(水)公開/1時間36分大映京都/白黒スタンダード
併映:「白い山脈」(記録映画)
| 製作 | 永田雅一 |
| 企画 | 辻久一 |
| 監督 | 吉村公三郎 |
| 原作 | 溝口健二(井原西鶴「日本永代蔵」「世間胸算用」「萬の文反古」より) |
| 脚本 | 依田義賢 |
| 撮影 | 杉山公平 |
| 美術 | 水谷浩・内藤昭 |
| 照明 | 岡本健一 |
| 録音 | 海原幸夫 |
| 音楽 | 伊福部昭 |
| 助監督 | 弘津三男 |
| スチール | 松浦康雄 |
| 服飾 | 上野芳生 |
| 出演 | 香川京子(近江屋娘・おなつ)、中村鴈治郎(近江屋の主人・仁兵衛)、中村玉緒(扇屋遊女・綾衣)、勝新太郎(鐙屋の倅・市之助)、林成年(近江屋の倅・吉太郎)、三益愛子(鐙屋の女主人・お徳)、東野英治郎(大名留守居役・星野権左衛門)、小野道子(扇屋遊女・滝野)、浪花千栄子(近江屋の女房・お筆)、山茶花究(大阪の両替商・河内屋)、十朱久雄(大阪の両替商・新屋) |
| 惹句 | 『色と欲につかれた人間の、赤裸な姿を鋭くつく!』『金さえあれば命もいらぬと云う 世にもあきれたケチンボウをめぐる人間性の悲劇・・・』 |
| ベストテン | キネマ旬報ベスト・テン第18位(ベスト・ワン「米」) |
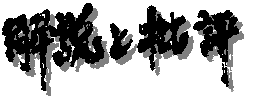
■ 作 品 解 説 ■
この映画は、故溝口健二監督が生前製作に着手したが、撮影開始直前に他界した。この偉業を吉村公三郎監督で、故人の霊にむくいるために製作された追悼映画である。江戸文学史上ユニークな存在として、いまなお文壇に多くの影響を持つ、ドライ派の文豪井原西鶴の「日本永代蔵」「世間胸算用」「万の文反古」より故人自身が「大阪物語」を書き、依田義賢と共同脚色したものである。
製作も永田雅一が陣頭指揮に立ち、撮影も幾多の国際賞に輝くベテラン杉山公平が当り、故人に捧げる追悼映画として吉村監督の総てを結集して製作された。内容は、徹底したケチンボの主人公が、なぜこうまでになったかを喜劇的に描く事に依って、人間本来の色と欲をえぐり出そうとする異色篇である。
配役もケチンボの主人公に関西梨園の名華中村鴈治郎、その子に林成年、母娘に浪花千栄子と香川京子、香川の恋人になる番頭に市川雷蔵が当るほか、三益愛子とその息子に勝新太郎、また遊女役には小野道子、中村玉緒とズバリ適役を揃えての豪華絢爛たるものである。
扮装も、又従来の時代劇の型を打破る生活臭さがにじみ出ており、吉村監督ならではの近代的センスで処理された新味が、一段と興味を増している。(公開当時のパンフレットより)

![]()



 サンスポ・大阪 03/04/57
サンスポ・大阪 03/04/57
| 林成年と共演の『花の兄弟』(子母澤原作、三隅研次監督/56年6月8日公開)をあげると、市川雷蔵は溝口健二監督の『大阪物語』に出演することとなっている。
『大阪物語』は元禄時代の有名な作家である井原西鶴が、四十七歳の元禄元年に発表した町人物の傑作「日本永大蔵」をもとに依田義賢が脚色したもので、溝口監督は、先にやはり西鶴の好色物の傑作「好色一代女」を『西鶴一代女』として映画化しているので、今度は二度目になるわけである。 「日本永大蔵」は町人の致富談を中心とする短編集で、全部で六巻、一巻に五話ずつ全三十話の短編を収めてある。いろいろ面白い話があるが、その中でも最もすぐれている一巻の第二話「二代目に破る扇の風」を中心に、各話をまとめて一つのストーリイに構成したものと思われる。「二代目に破る扇の」というのは、非常にケチンボで一代に二千貫ためた親爺に、更に輪をかけた吝息子が出来て、腹がへるからと火事の見舞いにも早く歩かぬような男だったのだが、道で女郎の手紙を拾って、ふとそれを届けたことから、放蕩者になって産をつぶしてしまう話である。 溝口監督は『大阪物語』で、金の亡者となった吝な親爺と、それに反抗する息子達の姿を、シンラツな眼でとらえようとする。簡単にストーリーを紹介してみよう。 |
|
X X X X X
近江の寒村に、妻と、兄妹の二人の子供を抱えて暮す貧乏な百姓の仁兵衛は、高利貸から借りた金が返せず、村から夜逃げしようとした。その途中、山の中で首を吊ろうとする一人の男を見るが、かけつけて来た身寄りの者が、金策のついた事を知らせると、地獄へ片足をつっこんだような今迄の深刻な顔はどこへやら大喜びで帰っていった。仁兵衛は、世の中は万事金だ、金さえあれば人の命も助けられる、金々々と金にとりつかれた男になってしまった。
大阪へ出た仁兵衛は堂島川の岸に荷あげの際こぼれる米を拾ってため、それを金にかえて、爪に火をともすような生活を永々十年、遂に近江屋と名乗る大きな両替屋の店を持つ迄になったが、吝な事は天下一品。小僧をつれて表へ出ても、草履を一寸引ずって歩いたりすると、早くちびるから、もっとソッと歩けと怒る様である。息子の吉太郎、娘のお夏も早や年頃になっていた。
ある日仁兵衛は、大工がカンナ屑をこぼしているのを見てたきつけにしようと小僧に拾わせようとしたが少しの違いで、油問屋の後家お徳に拾われてしまう。この後家が又仁兵衛に輪をかけた吝ン坊で、「カンナ屑をたきつけにするなど勿体ない、私は貯めておいて屋根を葺いた」「お宅は使用人に月に何べん魚を食わせます、えっ!十日に一ぺん、うちは一日と十五日とたった二へんですわ、朝のおかゆは十五人に五合、そんな勿体ない、うちでは二十人に五合です」とあらゆるものが仁兵衛以上、お互いに意気投合して話がはずみ、「どうでっしゃろ、お宅のお夏さんを、うちの息子の市之助の嫁に貰えまへんやろか」ということになる。仁兵衛は大喜びで二つ返事で承知してしまうが、お夏はかねて番頭の忠三郎と深い仲、親子喧嘩やら夫婦喧嘩やらで、かねて癆咳の気のあった仁兵衛の女房のお筆は、心気が高ぶって、血を吐いて倒れてしまう。が仁兵衛は、「どうせ医者も助からん云うてんねんやったら、薬のますだけ無駄や」とほったらかし、お筆はとうとう死んでしまう。死者の遺言だからと、通夜の客に飯もださず、葬式も至極カン略にすませてしまうが、たまたまお夏を見ようと葬式にやって来た市之助も、此の徹底さに呆れて、「お前あほらしいないか足洗いに新町へいこいこ」と吉太郎をさそって廓へしけこむ。市之助にはもとより瀧野という敵娼がある。吉太郎の敵娼に出たのが綾衣という太夫で、ウブな吉太郎大もてにもてる。
一方仁兵衛とお徳の間の、縁組みの話も着々はかどるが、お徳がお世辞で「裸でもよい」と云った言葉をそのままに、仁兵衛は何もなしの裸一つでお夏を嫁にやるというので、又おおもめ、そのくせ結納金が少いとか多いとかうるさい事。お夏は家にいたたまれなく、忠三郎と駈おちを決心する。又、吉太郎は吉太郎で、市之助のような道楽息子のところへ妹はやれぬ、その為には瀧野を身うけさせて市之助と逃がしてしまうのが早道と、忠三郎に計略を含めて、蔵の鍵を盗ませ、親爺の仁兵衛が命より大事な金蔵の金を盗み出し、市之助に瀧野を身うけさせて大散財をしてしまう。
ところがふとした事から仁兵衛が豆板銀を一枚道ばたの溝の中へおとし、夜通し忠三郎に探させたがわからない。それを見た吉太郎、あまり馬鹿々々しいので、自分の持っていた豆板銀を一枚、忠三郎にやり、溝の中から見つかった態にして仁兵衛のところへ持って行かせた事から、蔵の中の金を盗んだ一件がバレてしまった。豆板銀には刻印がうってあったのである。仁兵衛は気違いのようにカンカンになって怒る。吉太郎もお夏も、親爺に反抗してとうとう近江屋を飛び出してしまうことになる。
さて、しかし、浮世の風に当ってみると、吉太郎も、お夏も忠三郎も、今更のように金の有がたみと、親爺のえらさがわかってくる。しかし今更家へ帰るのもケタクソ悪い。死んだ犬の肉を黒やきにして、それを万病に利く名薬だと云って、吉太郎が売歩いていると聞いた病床の仁兵衛は、「流石にわしの息子や」とニッコリ笑って息を引きとってゆく。
以上が大体のあらすじである。尚、撮影開始迄には、幾多の推敲が重ねられるであろう。雷蔵は昨年溝口監督の『新平家物語』で、青年清盛に扮して非常な好演を見せた。あれ以来、是非機会があれば先生の作品に出たいと云っていた雷蔵である。それが今回かなったわけだ。
関西梨園の名門中村鴈治郎も仁兵衛の役で出演することになっているが、吉太郎に扮して雷蔵が再びどのような好演を見せるか、異色ある素材だけに、ファンのかける期待も又大きいものがある。(映画ファン56年7月号より)
.gif)


■ 物 語 ■
元禄の頃。−東近江の水呑百姓仁兵衛は、年貢米が納められぬままに代官所の催促に耐えかね、地主に何とかすがらんものと二人の子供ともども、女房のお筆と大阪に夜逃げして来たが、地主の蔵元“花屋”では奉公人たちに玄関払いを喰わされ、あてもなく去って行く。一度は一家心中を決心した仁兵衛夫婦も、船から米俵を荷あげする主佐堀川の岸でこぼれた米を拾い集めることを知ってやっと夕食にありつくことが出来た。
そして十年、−川岸で、筒落米を拾った仁兵衛は、それが積り積って今では堺筋に近江屋を名乗る茶屋を副業の両替商に出世したが、昔米を掻き集めるのに使ったという手扇と手箒には、朝夕の礼拝を忘れなかった。それのみか、いやというほど貧乏の辛さをなめた仁兵衛は、天井の写るようなお粥をすすりながら、一方では茶かすを集めさせ、それを新しいお茶に混ぜて売るという徹底したケンチンボ商人であった。しかし二人の子供も、いまは息子吉太郎、娘おなつとそれぞれ成人して、若旦那さん、とうさんと呼ばれる身分になっている。
貧農からゲジゲジ両替屋になった仁兵衛は、かって玄関先で惨々なめにあった花屋が取り潰しになった時、早速その後釜に入って鼻をあかしたが、大きな店舗に移ってからも彼の守銭奴振りはますます激しかった。正月の門松が大きいといっては番頭の忠三郎を怒鳴り、事始めにお筆やおなつが髪結いを呼んだといっては怒ってこれを追い返した仁兵衛は、着物も正月の三日間だけ大事に着て、あとはおなつの嫁入りに持たせて、生まれた子供に着せるようにまた「飾らなもろうても貰えんような所へは、嫁にやりまへん」と主張する。「搗きたての餅は目方がかさむから、水気のひいた正味のところを買うてこい」といった調子で、折角搗かせた餅も、乾いた餅と取りかえに丁稚を走らせるという有様である。さらに河内屋の肝入りで本両替の仲間入りした時も、新町の揚屋“扇屋”の座敷で大名家老や留守居役などに引き合わされたが、大名相手の貸銀はどんな質草があってもごめんと、御馳走だけを折詰に、さっさと引上げるというチャッカリ振りに河内屋ら一同は驚くほかはなかった。
ある日、近くの普請場を通りかかった仁兵衛は、そこに居合せた油問屋の女主人鐙屋のお徳と知合いなり、お徳が木切れを拾っては箸にして、問屋に卸していると聞いて、上には上があるものとお互いに意気投合、揚句の果てに、お徳は伜市之助の嫁におなつを貰えないかと早速縁談の申込みをする。仁兵衛は即座に快諾を得たものの女房お筆は大反対、結局夫婦喧嘩になってしまったが、激情したお筆はついに喀血、それ以来病の床に伏してしまう。ところが胸の病気には何ら薬を飲ませても医者を儲けさせるだけで無駄なことだと仁兵衛はいう。時には親父以上にケチだった息子の吉太郎も、さすがに今度は反対したが、おなつの必死の看護も空しく、お筆は録に薬も飲まずに息を引き取った。
鐙屋のお徳は市之助を連れて近江屋のお通夜に行くが、実はおなつの顔を見るためのお見合いもかねて出掛けたわけである。仁兵衛が仏の遺言だと称して、お通夜の客にはお茶だけしか出さぬという有様に一同は深く憤慨するが、市之助は気晴しに女郎買いにでも行こうと吉太郎を新町の扇屋へ誘う。放蕩息子の市之助には、かねて滝野というおなじみの遊女がいるが、ウブな吉太郎の方は何も知らず綾衣によって初めて女を体験する。最初はもじもじ怖がっていた吉太郎も、ついに綾衣の愛撫によって“極楽浄土だ”と上機嫌、その機につけこまれた吉太郎は滝野を見受けするための金を工面してくれと市之助から頼まれてしまった。
鐙屋との縁談をいやがっていたおなつは、番頭の忠三郎にかねてからの思いを告げ、ともに駈け落ちしてくれと迫るが、吉太郎は地下の蔵から銀を盗み出して市之助に渡したため、その金で滝野太夫を身受けして逃げてしまった。ところがこのことが仁兵衛の知るところとなり、盗難の嫌疑は二人の事情を知った忠三郎にかかるが、吉太郎は事の次第をぶちまけると、忠三郎とおなつを夫婦にしてやってくれという。怒りに燃えた仁兵衛は吉太郎に勘当を申しつけるとともに忠三郎にも出て行けと怒鳴る。おなつも後を慕って家出、独りぽっちになった仁兵衛は、蔵の中に閉じこもって、仁王立ちになったまま、ついに金箱を抱いて発狂してしまった。土佐堀川で忠三郎を見失ったおなつは、思い余って身を投げようとするが、吉太郎が無事引止め家に帰るように勧めるとともに、親爺が死んだ時の相続金は折半して吉太郎にも譲る旨を認めた証文に、おなつの血判をとるというチャッカリ振りである。この証文を懐ろに赤犬の黒焼きを、“熊の胃の薬はどうや”と売り歩く吉太郎の姿が、今日も琵琶湖を渡る船の中に見える。(公開当時のパンフレットより)
大阪物語 井沢淳
仁兵衛は水呑み百姓である。だから、妻と二人の子供をかかえて、年貢が納められぬ。もう納期が近づいて、どうしようもなくなった仁兵衛一家は途方に暮れるのだが、それを描くファーストシーンが、如何にも吉村公三郎らしくてうまい。じっと目を見開いている子供の大写し、それが、何かを捉えて、子供は一目散に走り出す。家へ飛び込んで、代官が来たことを告げると、カットが変って、のそりと代官が入って来る−。この呼吸は、吉村作品にしばしば見られる快適なもので、すでにして、ファーストシーンで見る者を引きつける力がある。
ただし、結論からさきにいうと、この『大阪物語』は、こういうスマートなファーストシーンを持ちながら、全体としては疑問が大いにある。それは、主人公のケチン坊ということが、中途では、立派な合理主義として描かれ、終りでは、金の亡者として、発狂するという構成である。これはシナリオとしても疑問があるわけだが、仁兵衛が金持ちになってから、ケチン坊ぶりを発揮する演出にも問題がある。例えば、仁兵衛が十文の金が足りないというので、使用人を怒鳴るところでも、仁兵衛の怒り方があたり前に見えるのだ。本当は、「たった十文のことで・・・」ということを観客に伝えねば意味がないのだ。あるいは、ドラマにしても、妻や娘や息子たちに何か仁兵衛の行動が白々しいものとして映るように描かかれねばならない。ところが、そういうものが、余りうまく出ていないのだ。
妻が死んで、近所の人が集まって来ているところでもそうだ。仁兵衛は妻の意志だといって、お茶しか出さないのだが、それは考えて見れば、集まった人々には、如何にも白々しい気持ちを与えるはずだ。映画は、それを集まった人々のなかの世話人を通して描く。この男が、何とも困り切った顔をして、「お茶しか出んそうや」というのが白々した短いカットだが、これはどうも淡白すぎたのではないか。どこかえげつない仁兵衛を外から描くためには、周りの人々が「興ざめした・・・」という気分を画面に浮き上がらせねばなるまい。
同じ大阪を扱った吉村作品『暴力』は、もっと油っ濃いものがあった。クジラの油で、安物のサカナをじゅーっと揚げているような生臭さがあった。それに比べると、『大阪物語』は非常にスマートなのだ。吉村公三郎の演出態度が、『夜の河』などを通して、インテリ的スマートさに向っているのではないかとも思う。そういう演出を通して形象化された仁兵衛は、金の亡者になるまえに、合理主義者として独り歩きする。すでに吉村公三郎の手を離れて、独立して存在する。だから、演出の糸が、仁兵衛を発狂の方に操って行っても、その通りには動かなくなってしまった。
仁兵衛の発狂は、息子に大金を持ち出され、娘に家出されることによって起る。しかし、ここまでわれわれが画面でつき合って来た仁兵衛は、こんなことで発狂するとは思えないのだ。彼は息子や娘に逃げられても、二人とも帰って来ることを信ずるような男だと思ったりもする。あるいは、金がなければ、息子だって、娘だって、結局は降参すると信じているような男があってもいいと思う。つまり、これは、ちょっと思いつきの考えだが、こういうことも考えたくなるような仁兵衛の性格なのだ。
われわれは、この場合、「ベニスの商人」のシャイロックを思い出したりする。あのシャイロックが何としてもコッケイなのに比べると、仁兵衛は見事な合理主義者なのだ。あるいは、いまの大阪の繁栄を築いた経済人の先祖ともいえるものだ。事実、見ている間に、題名の「大阪」ということの連想から、いまの巨大な大阪商人の系譜を思い出す。そうして、演出も、そういう意図で進められたのかと考え直したりもする。もし、そうなら、最後の発狂だけが余計なだけで、これはすぐれた出世物語にもなるのではないか。その辺のことを、吉村演出のスマートさということとは別に、検討して見る必要はありそうだ。興行価値:故溝口健二監督が映画化を企図していた作品を、吉村公三郎が映画化したということが、まずファンにはピンと来よう。ただ一般性に欠ける点があるから、売り込みには慎重を要する。(キネマ旬報から)
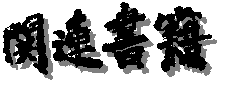

![]()


![]()