
ぼんち

1960年4月13日(水)公開/1時間45分大映京都/カラーシネマスコープ
併映:「扉を叩く子」(井上芳夫/川崎敬三・野添ひとみ)
| 製作 | 永田雅一 |
| 企画 | 辻久一 |
| 監督 | 市川崑 |
| 原作 | 山崎豊子(週刊「新潮」連載、新潮社版) |
| 脚本 | 和田夏十・市川崑 |
| 撮影 | 宮川一夫 |
| 美術 | 西岡善信 |
| 照明 | 岡本健一 |
| 録音 | 大角正夫 |
| 音楽 | 芥川也寸志 |
| 助監督 | 池広一夫 |
| スチール | 西地正満 |
| 出演 | 若尾文子(ぽん太)、 京マチ子(お福)、中村玉緒(弘子)、草笛光子(幾子)、越路吹雪(比沙子)、山田五十鈴(勢似)、船越英二(喜兵衛)、林成年(太郎)、中村雁治郎(春団子)、毛利菊枝(きの)、菅井一郎(工場主土合) |
| 惹句 | ①『女はこうしてくどくんや!金はこうして儲けるんや!』②『山崎豊子の最高傑作を、市川崑の鮮鋭な演出と、市川雷蔵の絶妙の演技で映画化!本年度ベストワンを狙う野心大作!』③『もう女に惚れるのはやめとこ思うたが、あかんまた惚れてしもうた!』④『雷蔵・市川崑の絶対コンビが、大阪商人の土性ッ骨と四ツに組んで、あくなき愛欲と気骨を描く野心文芸大作!』⑤『放蕩の限りをつくしても、その底にぴしりと帳尻の合った遊び方をする・・・・・それを大阪ではぼんちと呼ぶ!』⑥『女体遍歴にも商魂をかけたぼんちの根性!』⑦『女におぼれたかて、わてはソロバンは、ちゃんと、はじいているのや!』 |
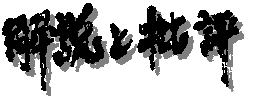
■ 解 説 ■
総天然色『ぼんち』は、市川崑監督、市川雷蔵『炎上』コンビで映画化する文芸巨篇であります。原作は一年間「週間新潮」に連載され好評を博し、単行本になるや、早くもベスト・セラーズとなった、山崎豊子の傑作小説であります。スタッフは製作永田雅一、企画辻久一、脚本和田夏十・市川崑、撮影宮川一夫、照明岡本健一、録音大角正夫、美術西岡善信、時代考証中村貞似、衣装考証上野芳生、編集西田重雄、音楽芥川也寸志のベスト・メンバーが顔を揃え、市川崑監督を助けることになっています。
雷蔵の喜久治をめぐる女優陣には、仲居頭お福に京マチ子、芸者ぽん太に若尾文子、妻弘子に中村玉緒、娘仲居幾子に草笛光子、女給比沙子に越路吹雪の新鮮な顔が揃えられている他、祖母きのに毛利菊枝、母勢似に山田五十鈴、父喜兵衛に船越英二、落語家春団子に中村雁治郎、工場主土合に菅井一郎らのベテランが、この作品に厚みを加えることになっています。
大阪船場のぼんちという宿命を負うた一人の青年が、昭和の激動期を如何にして生き抜いたかを、シャープなタッチで描く話題作でございます。( 公開当時のプレスシートより )
■ 物 語 ■
船場の足袋問屋河内屋のぼんち喜久治は、五十七才の現在、妾の子太郎に養われる境涯である。だが、その心の底にはうつぼつたる商魂が漲っており、時代の大きな流れが彼の考えなど押し流してしまったのに気付かず、旦那気分に浸っては、下手な落語家春団子などに昔を語るのを愉しみにしている。
四代続いた船場の足袋問屋河内屋の一人息子喜久治は、二十三才の時、祖母きの母勢似にすすめられ、砂糖問屋高野屋から弘子を嫁にもらった。河内屋は三代も養子旦那が続き、喜久治の父喜兵衛も番頭上りである。そのため、奥内をしきる、きのと勢似の力は絶対で、無気力な喜兵衛は女どものいいなりになり、商売一途に気をまぎらわせていた。
嫁の弘子をきのと勢似は、船場のしきたりとか、家風とかで、じりじりとしめつけた。弘子にはそれが耐えられなかった。そんな弘子にやさしい言葉をかける喜久治に、弘子は身悶えして訴えた。自分が便所にいったあと、必ずきのと勢似とが便所に行き、月のものの有無をたしかめている、というのである。妊娠した弘子は、病気と偽って実家に帰り、久次郎を生んだ。家風を無視されたきのと勢似は躍起となり、弘子を離別するようにはかった。この二人の女の身勝手さを喜久治はただ傍観するのみ。
昭和五年、父喜兵衛はふとした風がもとで寝込んでしまった。めっきりと弱った喜兵衛は、喜久治に「気根性のあるぼんちになってや、ぼんぼんで終ったらあかんで」とこんこんと悟すだった。弘子を離縁してからの喜久治は新町の花街に足をいれるようになった。待合冨の家の娘仲居幾子は、何かと喜久治に好意をよせ、経済的な遊びの方法を教えた。その幾子の口から喜兵衛に妾のあることを知った喜久治は、その妾君香を付添婦として、父の病床につけた。だが、この思いやりも甲斐なく、喜兵衛はきの、勢似に詫びつつ死んだ。君香の正体を知って躍起になるきのと勢似に、喜久治はこれも船場のしきたりだ、と冷たく言い放った。
父の死によって喜久治は五代目の河内屋の旦那におさまり、その襲名の宴を料亭浜ゆうで派手に開いた。この席をとりしきったのは仲居頭のお福である。お福の色白の惚れぼれする餅肌に、きのと勢似は魅せられ、この女を喜久治にとりもち娘を生まそうとひそかに画策した。祖母たちの身勝手さにたまりかねた喜久治は、待合金柳で、芸者ぽん太と出会った。ぽん太は十本の指に、ダイヤ、ルビー、エメラルドなどの指輪を、ぎっしりと集めている風変わりな芸者である。喜久治は即座に「わいが今日から指輪一本にしたるで」と、ぽん太をやんわり抱くのだった。
妾となったぽん太は、しきたりに従って本宅うかがいに現れた。親子二代の芸者だ、と誇らし気にいうぽん太に、さすがの勢似も気を呑まれた。一方喜久治は幾子が芸者に出たことを知るや、彼女を早速、鰻谷に囲ってしまった。ぽん太とちがって万事地味作りの幾子は、喜久治をよろこばすことだけを考える女だった。丸髷をゆった幾子をみていると、喜久治は妾宅に来ているのをふと忘れるほどだった。ぽん太に男の子が生まれた。これを知ったきのは、五万円の金で生れた子と縁切りをしてくるよう、冷たく言った。金で親子の縁を切る、さすがのぽん太もこの無情なしきたりに涙した。
支那事変が始まり世の中は不景気の一途を辿っていた。喜久治は、道頓堀のカフェ赤玉で、競馬に夢中の女給比沙子をみつけた。芸者遊びしか知らない喜久治には、思ったことをづけづけいう比沙子が新鮮なものに見えたのである。ひっそりと鰻谷の妾宅に納っている幾子も三十三才になった。厄年に初産を迎える幾子は女の厄除けの信心に夢中である。その幾子の口から厄除けの七色の紐のことを聞いた喜久治は、早速、七色の足袋の製造にかかった。だが、この思惑は見事にはずれた。
内心面白くない喜久治は、一日、比沙子と共に淀の競馬場に現れた。帰途、比沙子のアパートで喜久治は突然に発熱した。ようやく快方に向かった喜久治は、幾子の急死を知らされた。難産の後、子癇を起こしたのである。哀れな幾子のことを思うと、喜久治はじっとしておれない。だが、妾の葬式を旦那が出してやることは、しきたりが許さない。喜久治はやつれた体を引ずるようにして、浜ゆうに現れ、お福のはからいで、二階の納戸部屋から、幾子の葬式を見送った。初めて自分の女を死なす悲しさに、男泣きに泣く喜久治を、お福は自分の体を投げ出して慰めてやった。
支那事変から太平洋戦争へ。喜久治は灯火管制下にも、妾の家をこまめに廻りつづけた。途中憲兵につかまったりして、非国民呼ばわりされたが、喜久治はへこたれなかった。そんな喜久治を下請工場主土合は感心するのだった。
戦争が激化して、大阪も空襲に見舞われるようになった。喜久治はいやがるきのと、勢似を有馬へ疎開させた。だが遂に、船場も爆撃で火の海と化した。間口十間の大店舗を誇った河内屋も蔵一棟を残して全焼してしまった。茫然と佇む喜久治の許へ、ぽん太が体一つで現れた。続いて比沙子、お福もやってきた。皆が煤だらけの顔で、眼ばかりギラギラさせている。睨みあう女三人を蔵の二階へ追い上げ、前後策を練る喜久治の前に女中のお時に手をひかれた、きのと勢似と久次郎が帰ってきた。船場だけをよりどころにしていたきのは、船場が焼けたと聞いて、じっとしておれなかったのである。狭っくるしい一つ蔵の中で寝ている、祖母・母・息子・妾三人の寝姿をじっと見ていた喜久治は、突然何を思ったか、皆を叩き起こし、金庫の金を出して等分に分け、この金を持って河内長野の菩提寺へ行ってくれといった。翌朝きのは、西横堀川に水死体となって発見された。絶望のあげく自ら身を投じたのである。
漸く戦争も終り、商売の立直しに明け暮れしていた喜久治は、ふと、河内長野にいる、三人の妾がどうしているかと気にかかった。八月の暑いさかり、預けてある菩提寺を訪れた喜久治はその風呂場で、のびのびとしたお福、ぽん太、比沙子が嬌声をあげながら入浴しているのを、かいま見た。「これからは株の時代や、大阪へ出て株をやりたい」という比沙子。「屋形に二、三人の抱え妓を置いて商売しまっさ」というぽん太。「残りの金でのんびりここで暮しまっさ」というお福。勝手にしゃべりまくる、三人の女のあけすけの姿を、じっとみつめていた喜久治は、そのまま女にも逢わず大阪に帰った。今までそれぞれに味のあった女が、単に女という肉体をもった生物としかうつらなかった。これで放蕩も終りだと、さっぱりした気持ちになっていったのである。
昭和三十五年三月、今は五十七才の喜久治ではあるが、彼は彼なりに商売に対する夢を抱いている。だがぽん太の子太郎は今さら足袋屋でもないと、喜久治を嘲笑するのだった。( 公開当時のプレスシートより )
「ぼんち」で二度目の現代劇に出演した市川雷蔵
それがなにか現代的青年を感じさせる。変な御世辞などいわないところがいい。わがままな性格を感じさせるくせに、どこか憎めない。時代劇俳優としては、大映そのものの時代劇が不調なせいもあって、余り目立ったものを出さなかった。それでもスターとしては、京都では立派に通用していた。このまま、京都の町を威張って歩いていても、結構、まわりからチヤホヤされていたはずである。事実、長谷川一夫につぐスターだったわけだ。 ところが、彼の偉いことは、その地位に満足せず、いつも、なにかいい仕事をしたいと欲張っていたことだ。しかも、その欲張り方も、決してあせらず、適度のペースをもってなにかをつかもとしていたことである。普通なら中途であきらめるか、人気だけにおぼれてしまうところだが、それでは自分がだめになることを知っていたのだ。
それが「炎上」において、みんなの注目を浴びる原動力でもあった。市川崑が雷蔵を認めてくれたことが、彼の幸運のはじまりだが、映画俳優とは待つことなり-ということを彼は実践したのである。『炎上』でなくても、この態度なら、なにかいいものを、いつかは、つかみ出していたと思われる。今度はその市川崑と再び組んで、『ぼんち』をやった。崑=雷蔵コンビが、フォード=ウェイン・コンビみたいになるかどうか。どちらも、我のつよい二人が、どういう風にうまくやって行けるか、二人のためにもいい結果を祈りたい。(キネマ旬報より)
ミスキャストだから張り切るゾ!
「適役をえてうれしい」というのは、製作開始に当って監督が主演スターに与える儀礼的なきまり文句だが、反対に「はっきりいって、ミスキャストだと思う」とやってのけたのが『ぼんち』を市川雷蔵主演で映画化することになった市川崑監督。ところが、いわれたご本人の雷蔵は別におどろきもせず、アタマをかきながらこんなことをいう。
「イヤ、われながらそう思うんですよ。あの原作がある週刊誌に連載されるときいてすぐツバをつけてもらった。最初の二、三日はスゴくよかったんですが、そのうちにオヤオヤと思い出した。原作者の山崎豊子さんのねらいはいろいろあるでしょうが、なんといっても女を次々と変えていくという話ですからね。そのうちに後援会の人から“あの小説はあなたのものではない。キット失敗する”なんて大変なファンレターも来る始末で・・・」
ミスキャストはどうやらご本人も認めるところとなったが、この仕事を最初から“投げた”わけではなく、むしろその反対だ。「ミスキャストということはまだ、雷蔵にはやれんだろう、ということにもなる。そうなればぼくも演技者のハシクレとして、ファイトを燃やしますよ。どんな人物でもやる。やってみたいというのが俳優の根性ですからね。だから市川先生も“こんどはキミに初めて本当の演技を要求することになりそうだ”といっておられますよ」という。この話をきいたのは、彼の司会によって行われたさる五日のブルーリボン賞授賞式の祝賀パーティでの席上。喜びあふれる受賞者に刺激されたこともあろうが、とにかくたのもしいかぎりのファイトではあった。(「週刊読売」サイン帳より)
「ぼんち」出演について

雷蔵さんは『ぼんち』出演について次のように語っておりました。
-原作者山崎さんの大阪に対する愛情の深さは、大阪で育ったぼくにはよく解ります。大阪人のもつデリケートな味をどうにかして演技でだしたいものです。時代劇スタアのぼくが、現代劇に出る以上は、なるほどとファンの皆さんいも肯いて頂けるものにしたいものです。大阪弁はまず大丈夫と思うんですが・・・。物語は大阪を背景にしていても、その底を流れるものは現代の日本全国に通じるものでなければならないと思うんです。現代人の共感を呼ぶ人間を演技で浮き彫りに出来ればいいんですが・・・。
主人公喜久治が新町宗右ヱ門町という花街で遊ぶため見学に行きました。少年期を大阪で過ごしましたが、南の花街はあまり縁がありませんでした。昭和初期から新町宗右ヱ門町の花街の風俗、お茶屋遊びの方法など、色々参考になりました。そうしてみると大変難しいことになりそうだ。衣裳も、着物だけで二十四点用意されています。女物ではその変化も目立つんですが、男物はその点変りばえしない、その割には金がかかるので衣裳選びも大変なわけです。
何しろ、二十二才から五十七才までの時代の推移を演技で表現する必要もあるし・・・メーキャップその他、いろんな点で工夫をこらしています。市川監督のイメージに極力あうようぼくはぼくなりにやってみるつもりです。-
ぼんちについて語る
|
|
|
原作者:山崎豊子 |
| 大阪船場という所は、大阪商人のメッカの様なところで、そこに生きながら富と女の間に生活をかけた一人の土性骨のある大阪商人を描いたつもりです。女遊びでも帳尻をぴしりと合わすことだけは忘れない、根性のすわったいわば男性の一つの理想像です。 |
| 私がいかに大阪を愛しているか雷蔵さんも大阪で育たれたんですし、私の気持ちをお汲みとり下さっていい映画にしてください。 |
|
|
|
監督:市川崑 |
| 原作は昭和初期から戦後の長期だが、映画は約二時間以内にまとめるため原作を消化するにはこれを分析する必要がある。 |
| いずれにしても、風俗映画として終らせたくない。ぼんちという人間像を通して、船場の奥深くかくされた精密な生活を描き、時代の流れに抗しえずして、押し流された主人公がかもし出す人間喜劇を狙いたい。雷蔵君には22才~57才までやってもらう。 |
ユーモアあふれる風俗映画「ぼんち」
「ぼんち」はたいへんエネルギッシュな人間たちのなまぐさい人間関係を、きわめて冷静に演出することによって高級なマンガのようなユーモアを出した風俗映画の傑作である。初期の奇矯な笑いは影をひそめている。
大阪は商業都市として数百年にわたる長い伝統を持った大都市である。その歴史のなかで、大阪の商人たちは独特の気風を発達させてきた。そのひとつに、女系家族の発達ということがある。商店が繁栄をつづけるためには経営者が有能でなければならない。しかし、世襲制では相続者がつねに商人として有能であるとはかぎらない。そこで、もし息子が有能でなかったばあいには、従業員のなかのもっとも有能な男を娘の婿にして、これに事業を相続させるのである。このばあい、妻はわがままいっぱいに育ち、夫はひたすら働き者であるというような組み合わせがひとつの典型的なイメージになる。
日本の社会は封建的で男尊女卑の傾向が一般的であったが、地域的にはこういう特色もある。大阪はまた、古くから独自の文化を発達させ、とくに演劇には独自の伝統があるが、商人の家庭の女性の強い性格を中心にして展開されるドラマや喜劇が少なくない。こういう地方性や地域的な伝統、その土地にとくに発達している独特のものの考え方や風習、性格や人間関係というものは、映画の題材の宝庫である。
「ぼんち」の原作者山崎豊子は、関西出身の女流作家として、こうした大阪独特の商人気質をテーマにした小説を数篇書いており、これはその代表的なひとつである。これを脚色した和田夏十は、市川崑監督夫人であり、もっぱら市川崑監督のためだけにシナリオを書いている。もと映画のスクリプターであった彼女にシナリオを書くようにすすめたのは市川崑である。彼はシナリオを書きたがらない彼女にシナリオを書くよう強くすすめたことによって、自分は日本映画に相当の貢献をしたことになると思う、とNHKのインタビューで語っていた。そのあとで市川崑がつけ加えて言ったことがおもしろい。しかし夏十さんにシナリオを書いてもらうとたいへんなんです、登場人物の扱いなどで意見が食い違ったりすると、あなたがそういう考え方なのでこれ以上いっしょに生活できませんといって離婚話になったりすることがあるんですから-と。夫の市川崑監督のためにだけシナリオを書いている夫人であるが、たいへん個性のはっきりした、自説を強く主張する女性なのである。
「ぼんち」とは、大阪の上流の商人の息子の愛称である。市川雷蔵演じる主人公喜久治は足袋問屋河内屋の息子である。この家は彼の母(山田五十鈴)も祖母(毛利菊枝)も財産の相続人で、彼女たちの夫はいずれも雇人だったのである。だからこの家では母と祖母の権力が絶大で、喜久治の父(船越英二)は妻に対してまるで下僕のような態度である。彼はこの家の婿になってから懸命に働いて家の財産を倍増したことを誇りにしているが、病気で寝るのにも、妻と義母に対して申しわけないと言ってわびる。しかし妻と義母は彼のことなどまるで心配していない。喜久治は父に同情している。じつは父親に、八年も前から芸者の愛人がいたことを知ると、彼女を看護婦だと偽って父親の病室に入れて看病させてやったのもそのためである。父親は涙ぐんで感謝し、まもなく死ぬ。その時母が泣くと、祖母は彼女にこう言う。「あんな婿はんでもやっぱりたよりにしとったんかいな。泣き止み。いやらしい」
その前に、喜久治は母と祖母から嫁をもらえと強要されて、弘子(中村玉緒)という商人の娘と結婚する。しかし、この家の絶対的な権力者である母と祖母は、弘子をまるで下女のように使ったあげく従順でないからと追い出してしまったのである。喜久治は、こんな母と祖母がいてはもう結婚などできないと思う。そして多くの女性を愛人にする。まず、ぽん太(若尾文子)という芸者を妾にする。彼女はちゃんと河内屋にやってきて、喜久治の母と祖母に、喜久治の妾ですとていねいにあいさつをする。祖母はぽん太がきちんとあいさつをしたことを賞めて給与を出す。
つぎに幾子(草笛光子)という芸者も妾にする。カフェーで知った比沙子(越路吹雪)という女も愛人にする。母と祖母はこの三人目の女性も妾として給与を出さなければ世間体が悪いと言う。喜久治は、比沙子はたんなる愛人なのだからその必要はないとことわる。幾子が子どもを産んで死ぬ。祖母は喜久治に、お福(京マチ子)という女を妾にするように言う。女の子を生ませたい、よい女の子なら働き者の男を婿にして河内屋を繁栄させることができる、とうのである。しかしお福は子どものできない女だった。そう告白するお福と話しているうちに、喜久治はお福を好きになる。
喜久治はしかしドンファンではない。仕事もまじめにやり、商売に新しいアイデアを加えて成功する。ところが戦争になり、大阪は焼け、河内屋も蔵ひとつ残して焼けてしまう。喜久治は必死にこの蔵を守ったのである。そこへ、ぽん太、比沙子、お福、そして母と祖母がやってくる。女たちはみんな、喜久治を頼りにしている。喜久治は愛人たちに残っている金を平等に分けて、田舎のお寺で生活していてくれと言う。しかし祖母は河内屋が失われたことで絶望して死ぬ。
それから一年後、喜久治は大阪に残って懸命に働いて、やっとみんなが生活できるようにして、女たちをあずけた田舎のお寺へ行ってみる。そして、ふっと本堂の横の風呂場をのぞいてみると、ぽん太、比沙子、お福の三人がなかよく風呂に入っていて、いい気なおしゃべりをしている。じつに楽しそうになかよく将来の金儲けの話などしている彼女たちをのぞき見してそのまま大阪に帰り、翌日使いの者に手切金を持たせてやって、すっぱりと手を切る。あとで彼はその時の印象をつぎのように語る。
「・・・・・誰もが苦しかったあの時代も知らぬげに、艶ようむっちりと肥えてたわ。それぞれに味のある女(おなご)やったと思い返そうとしてみても、もう駄目やった。女という肉体を持った生物としか見えなんだ。わいは嬉しかったなあ。これが放蕩の終わりやという事が解った。こんなにさっぱりしたええ気持ちで女から足が洗えるとは思うてもみなんだよって」
こう回想する喜久治はすでに老人であるが、この回想がじつにぴったりくるほど、田舎のお寺の風呂場で嬉々としてなかよくおしゃべりしている美女たちの姿は意外性があっておもしろい。この映画は、たんに一人の好色な男の色事一代記としておもしろいのではない。むしろ主人公は、母権家庭の犠牲者としてふつうの結婚ができず、そのために何人もの妾を持つはめになったのであある。そういう一般常識とは違うところに、妾が旦那の母親にあいさつに行って手当てをもらうというような意外性も成り立っているし、妾同士が、愛情ぬきのプロの意識でなかよくしているという意外性も成り立つ。その意外性のクライマックスとして風呂場の場面があり、それがほのぼのとあたたかそうな湯のなかでの美女たちのが戯れ合っていて一幅の浮世絵のようになっていればいるほど、主人公にとっては虚脱感と解放感をこもごも味わうという複雑な気持ちになるわけである。
彼はたぶん、自分は母と祖母の犠牲者だという思いと、女三人を妾にして彼女たちを日陰者にしているという罪の意識とをこもごもに抱いていたのであろう。ところが女たちは、みんあで連合して彼を食いものにしたにすぎなかった。罪の意識などひとつも感じる必要はなかったのだ。そう思うと急に、女性に対する執着も消えてしまうというところが、また、おかしい。この風呂場の浮世絵ふうの官能的な画面が一転して、もう妾たちに産ませた二人の子どもに養われる貧しい裏店の老人になっている主人公の姿になるという切り換えは、明らかに仏教的な無常感をねらっているが、ひとつの特色のある社会風俗のなかの特異な人間関係を誇張して、意外また意外とたたみ込む話のおもしろさをたんのうさせられる映画だった。( 佐藤忠男 「日本映画の巨匠たちⅡ」学陽書房刊より )
|
岡田 晋 作家というものは、ある瞬間に重大な啓示をうけると、突然自分の世界がひらけるのであろうか。『炎上』以来、市川崑をとらえた新しいひらめきは、『鍵』『野火』につづく『ぼんち』においても、独自な自己の途を快調に進んでいる。 市川崑=和田夏十のチームは、まずシナリオにおいて、山崎豊子の原作を映画的に乗り越えようとした。『鍵』や『野火』と同様、ここでも彼等は、文学を否定的媒体として、映画だけの世界から、文学のもつオリジナルティをスクリーンに生かそうとしている。この作品の面白さは、まず基本的に脚本の鮮やかな映画的処理にあるとさえ考えてもよいだろう。 たとえば、全体を回想形式によって通したことである、一人の《ぼんち》という特殊な人生が、現在から過去へのパースペクティヴにおいてとらえられた結果、過ぎ去った時代の、過ぎ去った物語としてではなく、ぼくたちの生きる現在地点にしっかりと直結している。もしこの映画から回想形式のワクをはずしてしまったら、物語は単なる《ぼんち》の一代記、風俗的な人生の変転をしか現われなかったろう。カメラの視点は、ただそれを写す傍観者の眼となって、俳優の芝居を観客に伝える以外の何ものでもなかったろう。1960年に生きる男の口から物語をはじめ、その男の胸の中にカメラの視点をあわせる時、物語は1960年の現実に、生きて展開するアクチュアリティを獲得する。客観描写ではとらえられぬ時代の流れまでが、主人公の眼と体験を通じてハッキリ観客に意識される。 とくにこの回想形式を成功させたのは、回想を終えてからの、みごとな終止符であった。主人公(雷蔵)の話を聞き終わった団子(鴈治郎)が、何気なしに「その話みんなほんまでっか・・・」と聞き返す。雷蔵と鴈治郎が退場した後、息子の太郎が「お父はんは同じ話をくりかえして誰にでも話す」といった意味の言葉をもらし、古くから雷蔵に仕えている女中お時に、父の話をたしかめるかの如く、「お時さんはお父はんが好きやったのとちがうか・・・」と問いかける。その後、女中のナレーションになって、「旦那はんは良いお人で云々・・・」のうちに、場面は暗くなるわけだが、このシーンのセリフは、いずれも質問の形式で出されたまま、答えのないうちに終っている。主人公が語って来た約二時間の物語が、果して真実なのかつくりごとなかの。思い出というものは、いずれも無意識のうちに粉飾され、真偽のほどもわからなくなってくる。ウソかマコトか、それをせんさくしてみても意味がない。要するに事実はわからないのである。ただ主人公が、それを語ったということにおいて、ウソにせよマコトにせよ、主人公の体験から出て来たという点で、思い出は現在地点に生きるだろう。女中は、全篇を通じて影のように登場している。回想の中ではほとんど重要な役を演じないが、主人公の近くに、主人公を観察して生きている。回想が終った後、この女中によって全篇をしめくくったことは、主観的な思い出を客観化する、非常にすぐれたラスト・ショットであった。たとえ回想形式によって全篇を構成されていたとしても、このラスト・シーンがなかったら『ぼんち』の作品価値は半減していたにちがいない。 市川崑の演出は、ワン・ショットの構図、ショットとショットのつなぎ方に、独特な調子を出している。人物のアクション、ドラマの流れによってショットを切る従来の方法に対して、これはドラマや人物をつき放し、一切を視覚的なオブジェに変えてしまうような演出であった。ドラマのおこらない空間をながながと撮って、そこに一つの主観的構図をつくり出したり、人物のアクションやセリフを大胆に切り、次の無関係な場面につないだり、一見それらしく見せる自然主義的描写とは全くちがった、かわいた演出に統一されていた。それが主人公の思い出であり、思い出とは、主人公の体験の中で一切が非人間化されるエゴイスティックな世界であり、主人公の人間性が他を圧迫して、それだけが語られる物語の形式であるが故に、こうした演出のタッチは正しいと思う。ただ、これをあまりに推し進めると、一種の視覚的アブストラクションになり、対象のもつリアリティを歪曲するのではないだろうか。この映画を撮影している時、市川監督は「ショットをなかなか切ることができない」あるいは「ドラマを描きながら、その背後にある時代の流れを、さながら二重像のようにあわせて感じさせたい」と語っていた。その意図は、たしかに全篇を通じて理解できる。和田=市川シナリオには、最近歴史へ対する眼が強く感じられるようになった。演出のアブストラクションを救い、それを現実にもとめるのは、おそらくこういう歴史性の確実な把握だろう。 出演者雷蔵以下、演技陣もレベルがそろい、よく市川演出を生かしている。主人公をとりまく五人の女優たちは、各々個性を生かした適材な役柄で、キャスティングの苦心が充分むくいられていた。またスタッフも、監督の個性をよく生かし、とくに宮川一夫のカメラは、色彩、明暗、構図において、西岡善信の美術はシーンの造形的な構成において、市川演出の重要なファクターであった。興行価値:スタッフ、キャストともに豪華。油の乗った市川監督の演出ですぐれた作品となった。『痴人の愛』との併映で、封切はさらにヒット。(キネマ旬報より) |
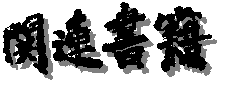
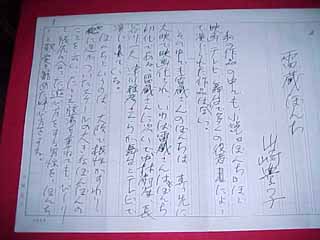
「雷蔵ぼんち」
私の作品の中でも、小説『ぼんち』ほど映画、テレビ、舞台で多くの役者によって演じられた作品は少ない。その中でも雷蔵さんのぼんちは、真っ先に大映で映画化され、いわば雷蔵さんはぼんち初代である。雷蔵さんに次いで、中村扇雀、長谷川一夫、津川雅彦さんらが舞台とテレビで演じている。
ぼんちというのは、大阪で根性がすわり、地に足がついたスケールの大きなぼんぼんのことを云い、たとえ放蕩を重ねても、びしりと帳尻の合った遊び方をする男性を“ぼんち”と敬愛を籠めた呼び方をする。
このぼんちは、大阪の船場という数百年の歴史を持つ街と、格式のある商家の特殊な風習の中から産み出された人間像であるから、たっぷりした豊かさと、気品がなければならない。ところが気品というのは、いかに芸達者でも、芸で作れるものではなく、自ら備っているものである。その点、雷蔵さんは梨園に育ち、いわば梨園のぼんちのような気品を身につけていた人であるから、映画化を申し入れられた時、迷うことなく快諾した。
たしか雷蔵さんにとっては、このぼんちが現代劇の主人公を演じる最初の映画であったと思う。それまで時代劇で水もしたたる美剣士ぶりは観ていたが、現代劇の主人公で、ぼんちをどのように演じるのか、非情に興味を持っていると、ぼんちの役作りについて、雷蔵さんから、私にどんどん注文が来た。

作品の中の河内屋のような古い商家を見学したい、大阪の花街、特に作品に出てくる新町のお茶屋へ上って、地の芸者に接して見たいという注文であった。幸い、その頃、船場育ちで遊び好きの亡き長兄が生きていたので、喜んで雷蔵さんを新町へ案内し、行きつけお茶屋に贔屓の芸者を揚げて、私も一緒になって遊んだ。
何しろ、市川雷蔵現われる、で、新町の芸者たちは「花代いりまへんよって、雷蔵さんのお座敷へ呼んでおくれやす」で、大騒ぎになり、五・六人の芸者の人選に、お女将さんが頭痛を起したくらいだった。
ところが、お座敷へ上った雷蔵さんは、最初のうちこそ、盃を傾けていたが、すぐ芸者の着物の着付けや所作を些細に見入り、ついには芸者に帯を解かし、長襦袢の伊達〆めの締め方を見、「なるほど、お座敷着の着付けも、京都の芸者とは違いますね」と云い、」さらに「小説の中の幾代が七色の腰紐を結ぶ、というあたりは、どういう工合に結びますのやろ」と聞いた雷蔵さんの芸熱心には、眼を瞠った。
そして、私は雷蔵さんに、ぼんちの役作りで一番難しいところはどこですかと聞くと、暫し考えてから、「女の道で苦労して、何かものを人に考えさせるような人間にならんとあかんー、という言葉が小説の中に書かれていますが、それを演技にするにはどうすれば・・・、つまり色道悟達の心理を演技するということは難しいことです」と答えられた。
それは作家が登場人物の心理描写に最も腐心し、苦労するのと同じ次元のことであるからだった。演技者としての市川雷蔵の姿がそこに見えた。若く美しく、気品に満ちた雷蔵ぼんちー、雷蔵さんは、私の作品を一作演じているだけだが、その一作は、数作に価するものであった。
その雷蔵さんは、私が外国にいる時、卒然とこの世を去ってしまわれた。葬礼にも詣れなかったが、私の瞼には、市川雷蔵さんの病んだ顔も柩の中の顔もなく、永遠に“雷蔵ぼんち”の顔だけが遺っている。(山崎豊子)
|
|
山崎豊子 1924(大正13)年生まれ。大阪府大阪市中央区出身。旧制京都女子専門学校(現在の京都女子大学)国文学科卒業。
大阪市の老舗昆布商店、小倉屋山本の家に生まれた。旧制女専を卒業後、毎日新聞社に入社した。大阪本社学芸部に勤務し、学芸副部長(当時)・井上靖のもとで記者としての訓練を受けた。勤務のかたわら小説を書きはじめ、1957(昭和32)年に生家の昆布屋をモデルに、親子二代の商人を主人公とした『暖簾』を刊行して作家デビュー。翌年吉本興業を創業した吉本せいをモデルにした『花のれん』により第39回直木賞受賞。新聞社を退職して作家生活に入る。 初期の作品は船場など大阪の風俗に密着した小説が多く、その頂点が足袋問屋の息子の放蕩・成長を描いた『ぼんち』であり、市川雷蔵主演により映画化された。さらに1963(昭和38)年より連載を始めた『白い巨塔』は大学病院の現実を描いた鋭い社会性で話題を呼び、田宮次郎主演で映画化されたほか、数回に亘りテレビドラマ化された。これも大阪大学医学部がモデルとなっており、大阪の風俗が作品への味付けとなっている。神戸銀行(現在の三井住友銀行)をモデルとした経済小説、『華麗なる一族』も佐分利信の主演で映画化され、さらに2度に亘りテレビドラマ化された。 その後、テーマ設定を大阪から離し、戦争の非人間性など社会問題一般に広げていった。『不毛地帯』、『二つの祖国』、『大地の子』の戦争3部作の後、日本航空社内の腐敗や航空機事故を扱った、『沈まぬ太陽を発表した。 1991()年、菊地寛賞受賞。最近では『文藝春秋』2005年1月号から2009年2月号まで西山事件をモデルとした『運命の人』を連載した。新潮社で『沈まぬ太陽』までの作品を収めた『山崎豊子全集』全23巻が刊行され、2005年に完結。2009年『運命の人』で毎日出版文化賞特別賞受賞。 『大地の子』で引退を考えたが、「芸能人には引退があるが、芸術家にはない、書きながら柩に入るのが作家だ」と新潮社の斎藤十一に言われ、執筆活動を継続している。書斎を「牢獄」と呼び、作品が脱稿すると「出獄!」と言って喜ぶという。 評価:「日本のバルザック」と呼ぶファンがいる一方、盗作疑惑が何度も指摘されている。参考とした資料をほとんど脚色せず作品に反映させたため、盗作との指摘を資料の執筆者から何度も指摘を受けている。よって盗作問題については、「資料の引用」とするか、「盗作」と取るか意見が分かれる所である。 フィクションに実話を織り込む手法は激しい批判を浴び、また『大地の子』をめぐって遠藤誉・筑波大学教授から自著「卡子(チャーズ)―出口なき大地―」に酷似しているとして訴えられる(遠藤誉『卡子の検証』明石書店を参照、なお訴訟自体は遠藤の敗訴が確定した)など、盗作疑惑がしばしば取りざたされた。1968年、『婦人公論』に連載中だった長篇小説『花宴』の一部分がレマルクの『凱旋門』に酷似していることを指摘された事件もその一つである。山崎は、秘書が資料を集めた際に起った手違いであると弁明したが、その後さらに芹沢光治良『巴里夫人』や中河与一『天の夕顔』からの盗用も判明したため日本文芸家協会から脱退した(1969年に再入会)。1973年には『サンデー毎日』連載中の『不毛地帯』で、今井源治『シベリアの歌』からの盗用があるとして問題となった。 |

![]()



![]()