
忠直卿行状記

1960年11月22日(火)公開/1時間34分大映京都/白黒シネマスコープ
併映:「わんぱく公子」(弘津三男/鶴見丈二・浦路洋子)
| 企画 | 財前武生 |
| 監督 | 森一生 |
| 原作 | 菊池寛 |
| 脚本 | 八尋不二 |
| 撮影 | 相坂操一 |
| 美術 | 西岡善信 |
| 照明 | 中岡源権 |
| 録音 | 林土太郎 |
| 音楽 | 伊福部昭 |
| 助監督 | 宮島八蔵 |
| スチール | 西地正満 |
| 出演 | 小林勝彦(浅水与四郎)、水谷八重子(清涼院)、中村鴈治郎(徳川家康)、山内敬子(志津)、林成年(森三十郎)、浦路洋子(香代)、三田登喜子(絹野)、丹羽又三郎(青木与四郎)、千葉敏郎(大島左太夫)、加茂良子(吉野)、清水元(忠源) |
| 惹句 | 『斬る!奪う!犯す!泣いて暴虐の限りをつくすは、乱心の果てか若き魂の反逆か!』『この愛が!この真実が!この苦難が!現代人の共感を激しくゆさぶる文芸巨篇』『酒乱に耽り、人妻を犯し、家臣を斬り捨てた悪名高き名君が、六十七万石と引きかえに、初めて掴んだ人生の真実!』『人妻犯し、忠臣を斬り、幕府に挑む!悲劇の大名が狂乱の中に求めた人のまこと!』『家来の忠義づらが憎い!女の媚が腹立たしい!乱行の限りをつくす若き大名が心に叫ぶ怒りと涙!』『城もいらぬ!名もいらぬ!乱行の忠直が求める人間の真実!』 |
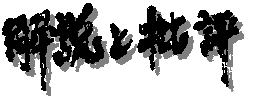
 『忠直卿行状記』
『忠直卿行状記』

![]()
忠直は彼にへつらい、何の抵抗をみせない家臣たちにいいしれぬ不満をいだいていた。その内面的な苦悩を知ってくれる者は誰一人としていない。そんな心理的演技にとりくむのは『大菩薩峠』で名演技を示した市川雷蔵さんです。「菊池寛の名作の一つに数えられるものを、どこまで自分で演れるかが一つの課題でしょう」と謙虚に語りながらも忠直に勝負する雷蔵さんです。
[ 解説 ]
大映では、初代社長、菊池寛の十三回忌を記念して、菊池寛の原作のなかから二本を選んで映画化することとなり、現代劇では、“時の氏神”を“新夫婦読本”として船越英二、叶順子の顔合せで映画化したことはすでに読者の皆さんもご存じの通り。これはその時代小説の映画化で、数多い菊池寛原作のなかでも、とくにその名の高い同名の小説から、時代劇のベテラン、八尋不ニが脚色したもの。スケールの大きな時代劇を放っている森一生監督がメガホンを握っている。そして、この主人公、松平忠直には、かねてからこの原作の映画化を強く望んでいた市川雷蔵が扮し熱演している。
ストーリーは、徳川家康の孫と生れ、大阪夏の陣では大阪方の軍師・真田幸村の首を討ち取るという武勲をたてた越前六十七万石の藩主、忠直が、家臣のふともらした一言から人生に対する不信の念を持ち、狂乱におちいる−というもの。そしてこの忠直が、はじめて人の誠を得たのは、六十七万石の大名の地位を去らねばならなかった時だった。
配役は、この忠直を真実にめざめさせる忠臣・与四郎にここのところたてつづけに大役を与えられている小林勝彦が、またその妻、志津には『鎮花祭』で大映入りした山内敬子が選ばれて初顔合わせをしているほか、丹羽又三郎、林成年、中村鴈治郎に、水谷八重子までが顔を見せる。
[ 梗概 ]
浅水与四郎は幼少から忠直の側近く仕える忠臣で、忠直附きの腰元志津と祝言をあげた。忠直は内外からその英邁振りをうたわれ、特に武芸に熱心で、よく家中の若者を集めて槍試合などを行った。
ある日、みずから白軍の大将となって出場した忠直は、紅軍の副将島左太夫、大将小野田右近を突き伏せた。ところがその晩、忠直が奥庭に出た時、昼間の二人が話す「以前ほど、勝ちをお譲りするのに骨が折れなくなった」という言葉を聞いて愕然となった。
翌日、急に槍試合を命じた忠直は、真槍で例の二人を傷つけてしまった。二人はほどなく割腹して果てた。生まれてこのかた自分の身に注いでくれる賞讃は偽りであり、家臣の追従であることを知って深い懐疑にとらわれた忠直の行動は、それからというもの暴虐非道を極めた。人妻を犯したり、諫言する家臣を斬り棄てるなど別人のような乱行がつづいた。これは不信に包まれた忠直が人生の真実を求めてさまよう悲痛な姿であった。
この行状は幕府の耳に入り、浅水与四郎は国家老本多土佐の命を受け、申し開きのため江戸へ発った。このことは忠直に対する不信であると正純に囁かれた忠直は、本多土佐を斬り棄て与四郎の妻志津を城中に監禁するが、志津はカンザシを片手に身を守った。
江戸から帰った与四郎はこれを知って城中に忍び込み、短剣を持って忠直に躍りかかった。敏捷無類、太刀を執っては家中第一と言われた必死の与四郎を忠直は見事に取り押さえた。忠直は自分の腕が確かであることを知った。与四郎夫婦の真実の姿も知ることが出来たが、初めて人生の真実を知った時はすでにおそく、忠直は六十七万石の大名を去らねばならぬ時であった。
母の清涼尼を上使として将軍家の上意は、領地召上げのうえ、その身は豊後府内にお預けという厳しいものであった。護送の役人に守られながら、配所へ赴く忠直卿の側には与四郎夫婦の姿があった。忠直の顔は流罪人とは思われぬほど明るかった。( キネマ旬報より )

忠直卿行状記 飯田心美
原作は菊池寛の小説中でも代表作となっているものである。ストーリーは封建制度の仕組のなかで君主と家臣とのつながりをながめ、それを若い領主の心に映じさせた話だ。他人を疑うことを知らずに育った純情な領主は、一日家臣たちのヒソヒソ話を立聞きし、自分に対する彼等の態度が虚偽とへつらい以外になかったことを知って愕然とする。
領主はその翌日から仮面の下にかくされた家臣の本性にふれようと焦りだす。その焦りは日毎に凶暴性を加えてギセイ者を続出させたが得たものは家臣の忍従ばかり、ついにその狂人にひとしい行状が幕府に知れ、免責処分ときまる。そのとき領主はようやく幼なじみの若夫婦によって真の人間性を知らされて我が心を取戻して処分に服す。
この構想は時代劇映画の題材としてもすぐれており、旨くまとまれば見ごたえある作になることは言うまでもない。ここではその主人公の領主忠直に市川雷蔵が扮し、適材として活躍するので一応水準には達しているのだが、率直にいうと、何か食い足りない印象が残るのを否定するわけにはいかない。原作がよかっただけにその原作者の意図をつたえるうえで映画化にあたり、もう一工夫あってほしかったという感じである。一口にいうとそれは文学移植にあたっての手続きの方法にあったと私には思われる。
主人公忠直が家来たちの本性を知ろうとあせりだす気持をめぐり、さまざまな問題が派生する可能性がある。まず領主という地位、家臣という存在、昔からのしきたりについての考えが忠直に浮かぶ。そしてそれを承知の上で人間の真実にふれようとする以上、暴走すればギセイ者が出るのは必至である。またそのギセイをめぐって、忠直側にも家臣側にも苦悩がわく筈である。文学の場合そういうことはすべて当事者の観念としてさばくことが出来るから描写も短くてすむが、映画の場合はどうさばくかが問題だ。だが、そこを素通りしてしまってはこの題材の核心にメスを入れずに終ることとなる。この映画を見ていて食い足りないのは、その肝心な個所のえぐり方、具象化の方法に描写の努力が注がれていないことである。努力といってわるければ、その個所に関するかぎり既に誰にも判り切ったこととして扱っていることである。その結果はどうなったかというと忠直の行状、つまり幾人かの死傷者乃至自決者を出すといった行動に共感をよび起さずに終っている。一見、なにか自分だけ純情のつもりでいる殿様のひとりよがりで終っているかに見えることは、この場合の扱い方として誤っていたのではないか。
その点この作は、心理描写のうえで筆の不足なところが見られた。雷蔵はタイプもよくはまり懸命な演技で好感がもてるし、若侍になる小林勝彦もよくやっている。また幕府の使者としてやってくる水谷八重子の忠直の母も終局の芝居をしめしている。要するに演出と脚本を担当した森一生、八尋不ニのもう一押しの工夫が足りないような気がした。興行価値:手堅い内容の作品で雷蔵人気も強いが、いささか題材が暗いため封切はのびなやんだ。(「キネマ旬報」より)

| 製作意図: 真実を求めて苦悩する若き藩主の悲劇を描く。(シナリオより) |
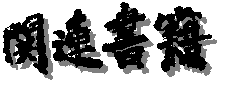

 菊池寛(1888 - 1948)
菊池寛(1888 - 1948)
松平忠直(1595-1650)を有名にしたのが菊池寛が1918(大正七)年に書いた「忠直卿行状記」である。大名ゆえの孤独で家臣が信じられなくなり、乱行がエスカレートし、自滅していく姿を描いている。さらに海音寺潮五郎も「悪人列伝」の中で乱行を強調し、「日本史上類例のない暴悪な君主」とまで書いてる。実際に三国港には妊婦の腹を裂いた時に使ったというまな板石だという石まである。また、福井には忠直を迷わせたという愛人一国の墓も残っている。
史実として、忠直は将軍家光の時代に、福井藩主の地位を追われ、豊後国府藩(現大分市)に流謫になった。忠直の息子光長は越後の高田(現上越市)に国替えとなり、福井藩は弟忠昌が継いだ。従って、忠直に問題があったのは間違いないところだ。福井だけでなく幕府に残る記録によると、参勤交代を怠り、途中までで出かけたにもかかわらず引き返したということも事実のようである。将軍の娘だった妻勝姫の付き人を殺したというのも、かなり信憑性がありそうだ。ただ最近の研究では、忠直の乱行伝説の多くは中国の故事をもとに後世に作られたものであり、一部問題があったとしても領地では名君だったという説も出ている。
インターネット図書館 あおぞら文庫「忠直卿行状記」(「菊池寛 短編と戯曲」文芸春秋1988(昭和63)年3月25日第1刷発行)を一読ありたい。
| ◆松平忠直
文禄4年(1595)年、摂津国東成郡生魂にて、結城秀康の長男として誕生。母は側室の中川氏。 慶長8(1603)年、江戸参勤のおりに叔父で江戸幕府2代将軍・徳川秀忠に初お目見得する。秀忠は大いに気に入り、三河守と呼んで自らの脇に置いたという。慶長12(1607)年、父・秀康の死に伴って越前75万石を相続し、慶長16(1611)年には秀忠の娘・勝姫を正室に迎える。元服の際には秀忠より偏諱を受け、忠直と名乗る。 慶長17(1612)年冬、重臣たちの確執が高じて武力鎮圧の大騒動となり、越前家中の者よりこれを直訴に及ぶに至る。祖父徳川家康・秀忠の両御所による直裁によって重臣の今村盛次(掃部)・清水方正(丹後)は配流となる一方、同じ重臣の本多富正(伊豆守)は逆に越前家の国政を補佐することを命じられた。翌慶長18(1613)年6月、家中騒動で再び直訴のことがあり、遂に富正が越前の国政を執ることとされ、加えて富正の一族・本多成重(丹下)を越前家に付属させた。これは騒動が重なるのは忠直が、まだ若く力量が至らぬと両御所が判断したためである(越前騒動)。 慶長19(1614)年の大坂冬の陣では、用兵の失敗を祖父・家康から責められたものの、夏の陣では真田信繁とされる首級を確保し、大坂城に攻め入るなどの戦功を挙げた。しかし、戦後の論功行賞に不満を抱き、次第に幕府への不満を募らせていった。 元和7(1621)年、病を理由に江戸への参勤を怠り、また翌元和8(1622)年には勝姫の殺害を企て、また、軍勢を差し向けて家臣を討つなどの乱行が目立つようになった。 元和9(1623)年、将軍・秀忠は忠直に隠居を命じた。隠居に応じない場合は軍勢を以て成敗すると脅し、秋田の佐竹義宣や加賀の前田利常には出陣の用意を要請している。忠直は生母の説得もあって隠居に応じ、隠居後は出家して一伯と名乗った。5月12日に竹中重義が藩主を務める豊後国府内藩(現在の大分県大分市)へ配流の上、謹慎となった。府内藩では領内の5,000石を与えられ、初め海沿いの萩原に住まい、3年後に内陸の津守に移った。津守に移ったのは、海に近い萩原からの海路での逃走を恐れたためとも言う。重義が別件で誅罰されると代わって府内藩主となった日根野吉明の預かり人となったという。 慶安3(1650)年に卒去、享年56。(Wikipedia) |
松平忠直像(浄土寺蔵)
|

![]()


