
眠狂四郎勝負

1964年1月9日(木)公開/1時間23分大映京都/カラーシネマスコープ
併映:「温泉女医」(木村恵吾/若尾文子・丸井太郎)
| 企画 | 辻久一 |
| 監督 | 三隅研次 |
| 原作 | 柴田錬三郎 |
| 脚本 | 星川清司 |
| 撮影 | 牧浦地志 |
| 美術 | 内藤昭 |
| 照明 | 山下礼二郎 |
| 録音 | 奥村雅弘 |
| 音楽 | 斎藤一郎 |
| 助監督 | 友枝稔議 |
| スチール | 藤岡輝夫 |
| 出演 | 藤村志保(妥女)、加藤嘉(朝比奈伊織)、高田美和(つや)、久保菜穂子(高姫)、戸田皓久(海老名良範)、成田純一郎(増子紋之助)、丹羽又三郎(神埼三郎次)、浜田雄史(赤座軍兵ヱ)、五味竜太郎(榊原喜平太)、浅野進治郎(柳生但馬守)、須賀不二男(白鳥主膳)、原聖四郎(和泉屋)、嵐三右ヱ門(大口屋)、橘公子(茶屋女) |
| 惹句 | 『斬るには惜しい相手だが・・・勝負は一瞬、鮮血飛んで、冷たく冴える円月殺法』『死ね!とひとこと・・・・血をふく敵に目もくれず、瞳は青く冴えている!』 |
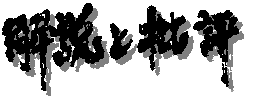
【作品解説】
狂四郎のキャラクターとシリーズの方向性を決定付けたとして評価の高い第二作。
物語は、私利私欲に溺れる高姫一派の策謀から清廉潔白な勘定奉行を守る狂四郎の活躍が主眼であるが、特に狂四郎と、彼の円月殺法を研究し尽くした榊原喜平太、海老名良範ら刺客たちの駆け引きが目を引く。
脚本は前作に引き続き星川清司が担当、狂四郎の住処を吉原裏の浄閑寺にするなど原作を離れた設定を盛り込み、星川独自の狂四郎像を自由に構築していった。監督は、伊藤大輔門下で時の大映時代劇を力強く牽引した三隅研次。本作品も、当時の大映時代劇に共通する様式美と、折り目正しき中にもダイナミズムを湛えた演出により大映京都カラーが横溢する出来栄えとなった。
中盤、狂四郎が霧深い深夜の境内で若き刺客たちを翻弄する件(狂四郎は姿を見せず声だけが響き渡る)は一種幻想的な趣の画作りで、三隅監督以下、撮影、美術、照明など各スタッフの技量が結実した名シーンのひとつであろう。撮影の牧浦地志と美術の内藤昭は『座頭市物語』で、照明の山下礼二郎は『剣』で三隅監督を支えた。
出演は高慢な高姫に久保菜穂子、謎めいた女占い師・采女に藤村志保、可憐なそば屋の娘つやに高田美和。打倒狂四郎に燃える刺客・榊原喜平太に五味竜太郎、同じく海老名良範に戸田皓久。また狂四郎と友情を交わす老勘定奉行に加藤嘉が扮した。


正月で賑わう愛宕神社の境内、石段に難渋する人々の尻を押して、小銭を稼ぐ少年がいた。少年に快く手伝って貰った好々爺風の老人は勘定奉行(加藤嘉)。群衆のなかにどこか虚無の影を宿し、黒羽二重の着流しで歩く無頼の浪人、眠狂四郎もいた。と、突然のスリ騒ぎ。雑踏に紛れ逃げて行く女スリが、次の瞬間全裸のあられもない姿を人目に曝す。狂四郎の刀が一瞬のうちに女スリの着物を剥いでしまったのだ。『眠狂四郎勝負』はこんなショッキングな場面から始まる。 監督の三隅研次は、シリーズ二作目のこの作品で、演技派として評価の高い市川雷蔵に、時代劇スターとしての魅力を存分に発揮させ、第一作では暗中模索だった眠狂四郎というニヒルな剣士の、しっかりした性格づけを行なおうとした。 戦後、柴田錬三郎が創造した狂四郎は、戦前の中里介山が生んだ机竜之介、戦中の吉川英治の宮本武蔵とともに、時代小説の三大スーパーヒーローだ。平然と人を斬り、女を犯す虚無性は、机竜之介と共通点はあるものの、狂四郎はモダニズムを持つのが新鮮に映った。 「孤独に堪えようとして、無明の道を歩む人間のドラマだ」と狙いを書く原作者は、狂四郎を異国の転びバテレンと旗本の娘の子という暗い出生に仕立てた。市川雷蔵は現代劇の『炎上』などで、屈折した青年僧をそれらしく演じるかと思うと、時代劇でいったん扮装すると、別人のように冷徹そのものの剣士なりおおせる、不思議な役者だ。三隅監督はそんな雷蔵の稀有な個性を、狂四郎像に巧みに重ね、この作品以後、狂四郎と言えばすぐ雷蔵を思い浮かべるほど、観客をひきつける魅力的な時代劇のヒーローを創るのに成功する。 狂四郎は、茶屋で知り合った朝比奈老人が、将軍の娘、高姫(久保菜穂子)の化粧料を節約したことから、白鳥主膳(須賀不二男)一味に命を狙われていると知るや、頼まれもしないのに朝比奈の用心棒を買って出る。このあたりの正義漢ぶりはニヒリストらしからぬが、そこが映画で、原作ほど非情無惨に徹しないのが、大衆受けしたのだろう。筋も波瀾万丈で、狂四郎の命と引き換えに夫の助命を願う女占師(藤村志保)、誇りを賭けて狂四郎に挑む槍の名手、榊原平太(五味龍太郎)をはじめ、主膳の意を受けた数名の浪士たちも狂四郎抹殺にかかり、ここに愛刀・無想正宗が緩やかに弧をを描く狂四郎の十八番“円月殺法”との、まさに勝負が展開する。 この映画の長所は、主演の市川雷蔵が市川寿海の養子になったとはいえ、幼時からさまざまな苦労を経てきた体験を、見事に内面化した演技力と、霧のなかでの死闘など“絵”になっている演出力だ。その陰には原作を思い切って改変、映画的シナリオ化した星川清司の脚本と、簡素な様式美を極めた内藤昭の美術がある。眠狂四郎という、どこか現代人好みのクールなダンディズムを身につけた時代劇の新ヒーローは、この一作から躍り出た。 (毎日新聞・大阪版 07/07/95) |
【物 語】
人の群れが不意に割れて、中からはじかれたように裸の女がとび出してきた。正月。あらゆる階層の雑多な参詣人でにぎわう江戸の愛宕神社の境内、懐中物を掏られた狂四郎が女の帯を衣裳をそして腰布まで切り落としたのである。平然と踵をかえす狂四郎の耳に、同じ境内の一角から“・・・尻押しつかまつろう”という少年の声が聞えた。茶屋女の話しによると町の剣術道場主である少年の父は、道場破りの男に殺され、揚句に道場も含めた家屋敷まで取られてしまったのだ。しかし、敵を討ちたい一心を秘めながら、境内の長い階段を登る参詣人の尻を押しながら己一人の食い扶持を稼いでいるというのだ。江戸の青空に飛ぶ凧を見詰めるそんな少年に狂四郎は声をかけた、「そなた、父の姿をもう一度、見たくはないか」と・・・。
狂四郎は茶屋に居た矍鑠とした老人を立会人に、少年を伴い道場へ向かった。そして見事に、少年の父の仇榊原左平次を少年の父の流儀である眼思流で倒したのだ。
少年のために一肌脱いだことで知り合ったこの老人とは、居酒屋で酒を酌み交わす仲となった。ところが、居酒屋をでたところで、“・・・くたばれ!”と吠える声がした。ただおろおろとしている年老いた侍に向って抜刀している浪人は、老人の前に現れた狂四郎と、束の間瞞め合ったが視線を外し、金儲けの機会は後にゆずると言い、赤座軍兵衛と名乗って去った。少し離れたところに、この場の様子を見守っている女占い師・采女の姿があった。
一向に風采のあがらぬ老人は狙われたのが二度目というのに手首にうけた傷より、頽廃した幕政と疲弊した世相を嘆いて口ごもっている、それが朝比奈伊織という勘定奉行の職にある男ときいて狂四郎は興味を唆られた。
翌日、朝比奈の邸に越後堀家の用人・白鳥主膳が訪れていた。用件は将軍・家斉の息女・高姫の廃止された高額な化粧代の復活であったが、主膳は朝比奈の手の包帯を横目に見て帰った。
狂四郎がいくつかの興味ある事実を知るのに大した時間は必要ではなかった。堀家に嫁いだが若くして主人を亡くした高姫は、白昼から美男の浪人・増子と屋形船で戯れる奔放かつ驕慢な性格の持ち主であること。高姫と堀家の用人・白鳥主膳は邪魔な朝比奈の暗殺を計画し、浪人・赤座はその刺客の一人であること。その上、主膳が札差、米問屋などに賄賂とひきかえに朝比奈の抹殺を約していることなど。朝比奈の人品に惚れ込んだ狂四郎は煙たがる朝比奈をよそに身辺警護を買って出た。
ある日、兄・左平次の仇と呼ばわりながら襲ってきた榊原喜平太の槍ににみまわれた狂四郎は、折から遊楽帰りの高姫の行列を見て、フッといたずらっ気を起し、槍を奪って橋の下に廻った。行列は橋中央で急に止った。狂四郎が突きあげた槍が高姫の太股を貫き、彼女の目の前で穂先が光っていたのだ。
狂四郎は、主膳が高姫の怒りを利用して、さらに手練の殺人者をくり出してくることを予想する一方、明日のいのちも顧みず、頑なに幕政改革を試みている朝比奈老人の頼りなげな様を思い合わせ、むしろ楽しげに笑みをうかべた。その狂四郎の前に現われた三人目は海老名と名乗る浪人。剣一筋に生きてきた、泰平の世の余計者、円月殺法を見たいという変わり者。
新に募った神崎を加えた赤座、増子、榊原、海老名と五人の殺人者が揃った。これらの狩り集めには、禁制のキリスト教を布教して囚われている異国人の夫を救うため、節を曲げて主膳の膝下にある采女がからんでいた。五人の殺人者はそれぞれ性格、武術流儀も又動機も夫々であった。
夜の町をぶらぶら歩きする狂四郎の前に采女が現われ、吉原中万字で、血、と謎めいた誘いの言葉を残して闇に消えた。狂四郎は陥穽と知りながら、吉原遊郭に赴いた。だが、五人は未だ暗殺謀議が整わず、逆に虚をつかれてしまったが、互いにあらためて対決することの宣言を交わして、この場は別れた。
狂四郎は、巣にしている投込寺浄閑寺への帰路、吉原堤で久しぶりにつやの屋台でそばを食べていた。いつの間にか降り出した雪の中で、狂四郎を見つめるつやの目は生き生きと輝いていた。その目が恐怖の色で大きく瞠らされた。槍をもった榊原が狂四郎の背後に現われたのである。対峙したまま化石のように動かぬ二人の体が、跳躍して入れかわった一瞬に勝負はきまった。
それから三日とたたぬうちに、又采女が狂四郎の前に現われた。精霊のような妖しい横顔をみせる女の誘いにのって茶を喫したのは不覚であった。狂四郎は両手を縛られ、高姫の褥の傍らに据えられるハメにおちいったのだった。
打掛をすて帯を解いて、なぶりものにしようとする高姫の艶然たる目を冷やかに見返し、あまつさえ痛烈な啖呵を浴びせられ、はじめて誇りを傷つけられた高姫の怒りが頂点に達した時、襖が開いて増子の手裏剣が飛んできた。辛うじて両手首の縄目で受け止めた狂四郎は、手の内の手裏剣が尽きた増子に体当たりを喰らわして逆に縄目の手裏剣で彼の喉笛を突き刺した。豪華で凄惨な死の部屋で高姫を人質にした狂四郎は、騒ぐ奥女中や家来達を尻目にまんまと脱出に成功したのだった。
第三の刺客は、町風呂の石榴口から浴槽の狂四郎を狙い、湯気の中に白刃をひっさげて現われた。この土壇場の危機は、予期せぬ采女の裏切りで救われた。采女自身にも解らぬという女心の不思議のなせることだった。
三度も失敗に終った狂四郎と朝比奈抹殺に、主膳は御前試合の名のもとに狂四郎と柳生但馬守との立会いを計った。奸計に他ならなかった。ところが、高姫の目前で息絶えたのは、狂四郎の手許に柄を残して飛んだ白刃に胸を貫かれた大口屋であった。
高姫ははじめて見せる柔らかな愁いの色をうかべながら、敗北を認め、浪人狂四郎に心を奪われたことを告白して静に笑った。・・・が、主膳は、裏切った采女を囮に、なおも闘いを挑んできた。
采女は武蔵野の渺々たる枯野原の只中に十字の木に縛りつけられていた。近づかないよう危険を知らせる采女の絶叫にも拘わらず歩を進める狂四郎の周囲には、遠く近く主膳の配下の者が潜んでいた。その中に赤座と海老名もいた。
最期の対決の時が刻々と肌身に迫り、辺りには殺気をはらんだ冷たい風が流れてきた・・・。(公開当時のプレスシートより)
前作の「殺法帖」のときには、いろいろ悪口を述べたが、この第二作は、見違えるようにスッキリした作品に仕上っている。筋立ても単純なものを使用して、これに描写で肉づけをするなど、娯楽作品の好見本といっても過言ではない。 狂四郎のほかに、もう一人主人公を作ったことも成功の一因だろう。この人物は、腐敗した幕政の改革に乗り出した老勘定奉行だが、この人物を紋切り型の正義漢にせず、およそ風采のあがらない、ひょうひょうとした老人に設定したところが、この映画のおもしろさである。 加藤嘉の好演が、とかく単調になりがちな時代劇に、アクセントをつけている点は見のがせぬ。 映画の見せ場は、狂四郎が五人の剣客と一人ずつ対決する場面である。槍を使う者、手裏剣の名人、剣の達人など、五人の剣客の個性と流儀を描き出したところも興味をひくし、立回りになかなか工夫を凝らしたのもおもしろい。 ことに、風呂のなかで、狂四郎が剣客を切り倒す場面や、ラストの剣客の首領格と戦うあたりはすぐれたできばえといえる。首領格の浪人は、狂四郎の太刀さばきを見て、彼を倒す方法は、狂四郎の剣が円を書きおわるのを待つ以外にないことをさとる。が、いざ自分が対決してみると、どうしても円を書きおわるまで待つことができない。そうして、彼は、結局は円月殺法にまきこまれてしまうのだが、そのようすを画面はかなりうまく描いている。 娯楽時代劇として面白くまとまった作品である。かなりの客筋もつかんでいて、興行価値70%台。(キネマ旬報より) |
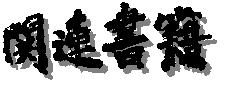
歴史読本1994年11月特別増刊号[スペシャル48]RAIZO 「眠狂四郎」の世界に詳しい。また、シリーズ映画「眠狂四郎シリーズ」参照。



![]()